そもそも得意なこと、って何?
まず「得意なこと」とは、自分が負担なくスムーズにできて、かつ周囲からも高く評価されやすいスキルや特性のことを指します。本人にとっては“当たり前”にできることであっても、他の人からすると「どうしてそんなに簡単にできるの?」と不思議に感じるものかもしれません。自分では気づきづらい長所でもあるため、まずは「得意なこと」を見つける重要性を押さえましょう。
強みや好みとの違い
「得意なこと」は、自分の中の“強み”や“好きなこと”と混同されがちですが、それぞれ微妙な違いがあります。強みとは“能力”や“性格的な長所”を指し、好きなことは“興味・関心が高く楽しめるもの”です。一方で得意なことは、好き嫌いを超えて「自然と結果が出やすい」「他人よりもスムーズにできる」ことを意味します。好きなことが得意につながる場合も多いですが、必ずしもイコールではありません。
「スキル」「資格」が得意なこととは限らない
「〇〇の資格を持っているから得意」「このスキルを習得したから得意」と思い込むのは、実は少し危険です。資格やスキルはあくまで知識や技術の証明ですが、それを使いこなして成果を出せるかは別の話。むしろ資格を持っていなくても、「現場で経験を積みながら自然と身につけたやり方」のほうが得意だった、というケースもよくあります。「得意=資格やスキルそのもの」ではなく、「得意=結果を出しやすい方法や思考」と考えるとわかりやすいでしょう。
得意なことを見つけるための3つのステップ
1. 過去と今の仕事を棚卸ししよう
自分が関わってきた仕事や活動を振り返り、“得意だった業務”や“失敗が少なかったタスク”をリストアップしましょう。成功だけでなく「気づけばよく任されていた仕事」などを見直すのもポイントです。思い返すことで、自分が自然とこなせていたことを再認識できます。
2. ラクにできることと苦痛に感じることを分ける
棚卸しした業務を、「負担なくできた」「やりやすかった」というグループと、「手間取り苦しかった」というグループに分けてみます。前者こそが得意な領域のヒントです。できるだけ感覚的に「ラクだったか」「しんどかったか」で分けることが大切です。
3. ラクにできることの特徴を探る
「ラクだった業務」の共通点は何でしょうか? たとえば「文章を書くことは苦にならない」「人と話しているときにアイデアが湧く」など、自分特有のパターンを見つけてみます。そこに得意分野が隠れています。
得意なことを発掘する7つのアプローチ
1. 「楽しい」と思える瞬間を振り返る
「時間を忘れて没頭できる」「やっている最中はワクワクする」と感じられる活動を洗い出しましょう。楽しいと感じられることには、自然とエネルギーを注げるため、結果的に得意になることが多いです。
2. 過去の成功エピソードや感謝された体験を振り返る
「周囲に褒められた」「上司や仲間に感謝された」という具体的な出来事から、自分の強みや得意を探ります。第三者からのポジティブな評価は、得意な領域を見極める大きなヒントになります。
3. 継続している好きなことを考える
どんなに忙しくても「続けられている趣味や活動」はありませんか? 続くということは、それだけストレスが少なく楽しめている証拠。趣味を通じて磨かれた力が、実は仕事でも役立つ可能性があります。
4. 苦手から逆算する
「嫌い」「苦手」と感じることを逆手に取り、その反対を考えてみるのも手です。たとえば、「人前で話すのが苦手」なら、代わりに「一対一で深く話すことは得意かもしれない」といった具合に、苦手の裏に隠れた得意を探してみましょう。
5. 周囲の意見を参考にする
同僚や友人、家族に「私の得意って何だと思う?」と聞いてみると、自分では当然すぎて気づかなかった強みを指摘されることがあります。第三者の視点は、意外な発見につながります。
6. 苛立ちを覚えた場面からヒントを得る
「自分は簡単だと思うのに、なぜあの人はできないんだろう?」とイラっとしたことがあるなら、そこに得意な分野が隠れているかもしれません。自分にとって当たり前のことが、実は他人にとっては難しい作業であることが多いからです。
7. 自己分析ツールを活かす
Web上には無料で使える自己分析ツールが多数あります。あわせて「性格診断」「ストレングスファインダー」などを利用し、客観的なデータから得意を見つけるのもおすすめです。
得意を仕事やプライベートに活かす3つのコツ
1. 自分の得意を「武器」として活用する
得意なことは、ビジネスや日常の課題を乗り越えるための強力な武器です。たとえば「情報収集が得意」なら、専門分野のリサーチを任されることでチーム貢献度が上がり、評価につながるかもしれません。積極的にアピールし、活かす場を探しましょう。
2. あなたの得意が活かせる環境・仕事を選ぶ
同じスキルでも、働く環境や業界によって評価され方は変わります。自分の得意が高く評価される環境を見極めることで、キャリアをよりスムーズに進められるでしょう。転職や配置転換を考える際は、自己分析の結果をもとにマッチする職場かどうかを検討してみてください。
3. 失敗を恐れず新しいチャレンジをする
得意なことが活かせそうな新しい仕事やプロジェクトがあれば、積極的に手を挙げてみましょう。初めはうまくいかなくても、チャレンジを通じて得意をさらに磨くチャンスになります。失敗を恐れて何もしないままだと、成長の機会を逃してしまいます。
「得意なんてない」と感じる3つの理由と対処法
1. 他人との比較に囚われている
「周りのほうが優れている」「自分なんて大したことない」と、人と比べすぎると自信を失い、得意を見逃しがちに。まずは自分自身の足元を見つめ直し、「自分がラクにできること」にフォーカスしましょう。
2. 理想が高くハードルが上がっている
「得意と言えるレベルって、相当すごくないといけない」と思い込むと、なかなか自分の能力を認められません。完璧である必要はなく、少しでも人より得意な部分や“よく褒められるポイント”に注目すると、意外と多く見つかります。
3. 当たり前にできることを見過ごしている
自分にとっては当たり前すぎて意識していない作業や行動も、他人からすると「すごい!」と感じられる場合があります。たとえば「資料をまとめるのが早い」「人前で話すのに緊張しない」など、一度“当たり前リスト”を作る感覚で書き出してみてください。
得意を自覚する3つのメリット
1. 自己肯定感が高まって自信につながる
自分が得意なことを認めると、「自分には強みがある」と思えるようになります。その結果、自己肯定感が高まり、新しい挑戦をするモチベーションもアップします。
2. やりたいことが明確になり行動に移しやすい
得意なことを活かせる場や仕事が見えてくると、将来の方向性がはっきりしてきます。行動の軸が定まることで、転職・異動・副業などの選択肢が具体的に検討しやすくなるでしょう。
3. 成果を出しやすく周りからの評価もアップ
得意な分野であれば、少ない労力で大きな成果を上げやすいもの。結果的に上司や同僚、取引先などからの評価が高まり、キャリアアップにもつながりやすくなります。
得意を知らない3つのリスク
1. 自己肯定感が低くなり自信を失う
自分の得意を認識していないと、長所がないような気分に陥りやすく、常に自信が持てない状態に。ネガティブ思考が続くと行動力も下がり、好機を逃してしまうかもしれません。
2. キャリアのチャンスを逃しかねない
「本当は向いていた分野」や「得意が活かせる職場」が目の前にあっても、自分で得意を把握していないと気づけません。せっかくの好条件を見過ごし、遠回りな転職やキャリア選択につながる可能性があります。
3. 成長や挑戦の機会を狭めてしまう
得意なことを起点に新しいスキルや経験を広げていくのは、キャリアアップにとっても大きなメリット。逆に得意を知らないと、自分が伸ばしやすいスキルセットを認識できず、結果として成長の機会を逃すリスクがあります。
よくある疑問:得意なことの見つけ方
Q1. 客観的に自分の得意を把握するには?
A. 家族や友人、同僚など身近な人に「私の得意って何?」と尋ねてみましょう。第三者の意見は、本人が気づかない視点を提供してくれます。また、自己分析ツールや適性検査を併用するのも効果的です。
Q2. 自分の強みを見出すには?
A. 「これまでに高い成果を上げた経験」「何度も褒められた経験」「難なく続けられている趣味・タスク」を振り返りましょう。小さな成功体験や「好きでやっていること」にも強みが潜んでいます。
Q3. 自分にできることを見つける手段は?
A. まずは職務経歴や学習経験などをすべて書き出し、“得意・苦手”に分類してみましょう。そのうえで、得意な項目について「さらに深堀りできる学習や資格はないか」「どのように生かせるか」を考えると、次のアクションが明確になります。
まとめ:得意を見つける7つの方法
「得意なこと」は自分では気づきづらいものの、しっかり棚卸ししたり他人の意見を取り入れたりすることで見つけやすくなります。上記で紹介した7つのアプローチを活用し、得意を確立しておくと、自己肯定感やキャリアの可能性が大きく変わってくるはずです。
• 棚卸しから始める3ステップでまずは「ラクにできる」部分を洗い出す
• 7つのアプローチを通じてさまざまな角度から得意を発掘する
• 見つけた得意は、自分の「武器」として積極的に活用する
得意分野を把握することで、自分が本来もっている才能や力を余すことなく発揮できるようになります。まずは小さなことからでも試してみてください。きっとこれまで見落としていた自分の強みに出会えるはずです。

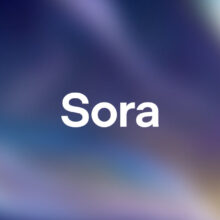

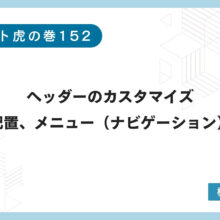
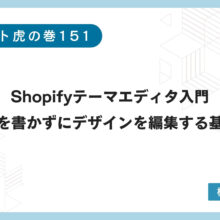
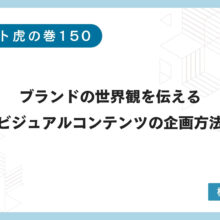
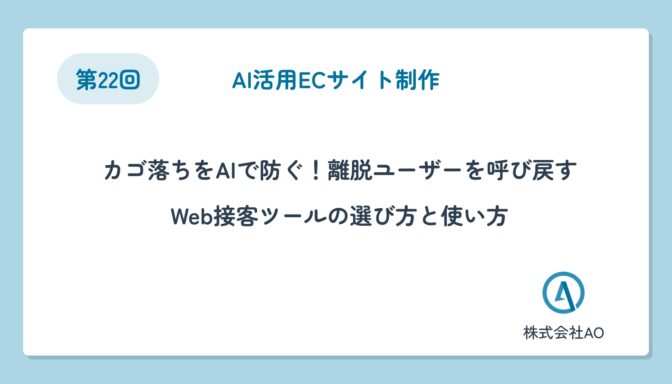


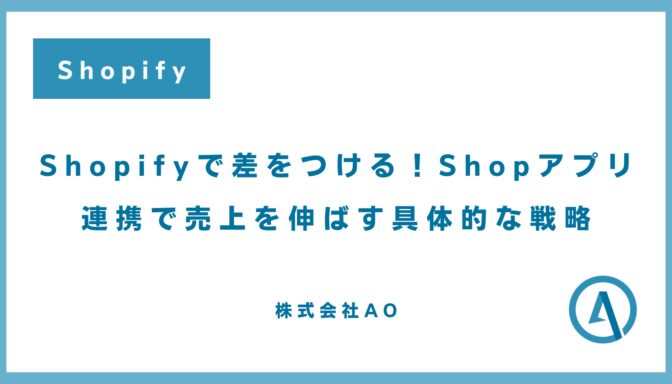









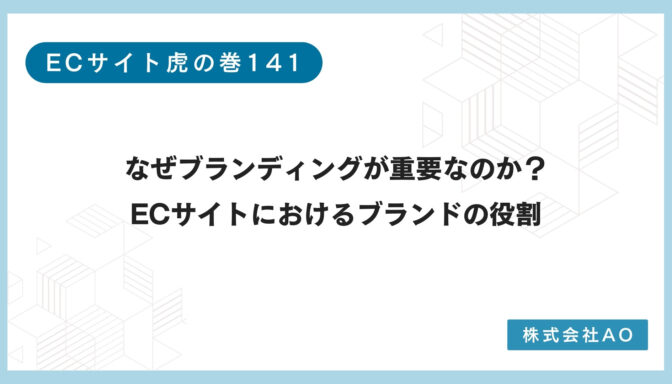
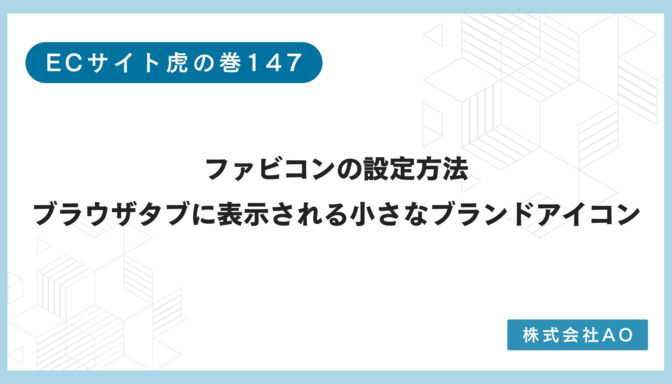
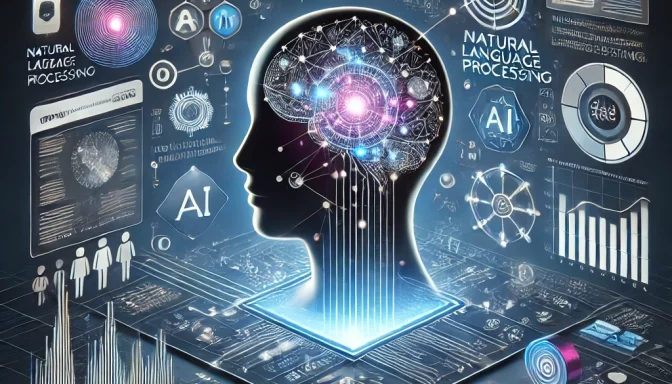



コメント