原価計算の基本的な考え方
「売上はあるのに、なぜか利益が残らない…」その原因は、どんぶり勘定の原価計算にあるかもしれません。適切な価格設定の第一歩は、商品一つにかかる本当のコスト=原価を正確に把握することです。原価は大きく3つの要素に分けられます。
直接費:製品に直接かかる費用
直接費とは、製品一つを作るために直接必要となる費用のことです。具体的には、商品の材料費や部品代、商品を仕入れる際の仕入れ費などがこれにあたります。比較的計算しやすく、原価計算の基本となる部分です。
間接費:見えにくい共通の費用
間接費は、製品に直接関連付けるのが難しい、事業運営に共通してかかる費用です。例えば、家賃や水道光熱費、通信費、梱包資材費、広告宣伝費などが該当します。これらの費用を製品一つあたりに按分して加算しないと、正しい原価は算出できません。
忘れがちな人件費も忘れずに
個人事業主や小規模なビジネスで特に見落とされがちなのが、経営者自身やスタッフの人件費です。制作や販売にかかった時間に、ご自身で設定した時給を掛け合わせたものを、れっきとしたコストとして計上しましょう。これを無視すると「タダ働き」の状態になってしまいます。
簡単!販売価格の計算ステップ
原価の構成要素が理解できたら、次は実際に販売価格を計算していきましょう。難しい会計知識は不要です。以下の3つのステップに沿って、論理的に価格を導き出すことができます。
STEP1:総原価を算出する
まず、製品一つあたりの総原価を計算します。これは、前項で解説した「直接費」「間接費」「人件費」をすべて合計したものです。これが、赤字にならないための最低ラインの金額、すなわち損益分岐点となります。
【総原価 = 直接費 + 間接費 + 人件費】
STEP2:確保したい利益額を決める
次に、製品一つを販売した際に、いくらの利益を確保したいかを決めます。この利益が、事業の成長や将来への投資の源泉となります。初めは、総原価の20%〜50%など、目標とする利益率(原価率)を基準に設定するのが分かりやすいでしょう。
STEP3:原価と利益から価格を設定
最後に、算出した総原価と、確保したい利益額を足し合わせます。この合計金額が、販売すべき価格の基準となります。この計算式で導き出した価格が、あなたのビジネスを支える土台となるのです。
【販売価格 = 総原価 + 確保したい利益額】
利益を最大化する価格設定戦略
計算で導き出した価格はあくまで基準です。市場の状況や商品の価値に応じて調整することで、利益をさらに最大化することが可能です。ここでは3つの代表的な戦略を紹介します。
競合の価格をリサーチする
自社の商品と似たような商品を、競合他社がいくらで販売しているかを調査します。市場の相場観を把握することで、自社の価格が高すぎないか、あるいは安すぎて価値を損なっていないかを確認できます。ポジショニングを明確にするための重要な工程です。
商品の付加価値を価格に反映
価格は、コストだけで決まるものではありません。優れたデザイン、高品質な素材、手厚いサポートなど、他社にはない独自の「付加価値」があるのであれば、それを自信を持って価格に反映させましょう。価値が伝われば、顧客は相場より高くても納得して購入してくれます。
心理学を利用した価格設定
お客様の購入心理に働きかける価格設定も有効です。例えば、10,000円ではなく9,800円に設定する「端数価格」は、お得感を演出する古典的な手法です。また、「松竹梅」のように3段階の価格帯を用意し、中間の商品を選びやすくさせる方法もあります。
まとめ:自信ある価格設定を
商品の価格設定は、単なる数字決めではありません。それは、あなたの製品の価値を定義し、ビジネスの未来を築くための重要な経営戦略です。これまで解説した原価計算の方法を実践し、自社の製品やサービスに込められた価値を正しく反映した、自信と根拠のある価格設定を行いましょう。それが、お客様からの信頼と、事業の継続的な成長に繋がるはずです。
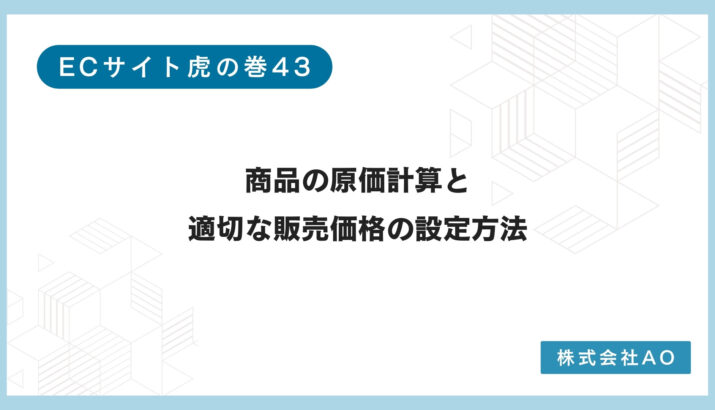
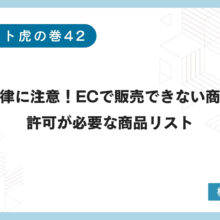
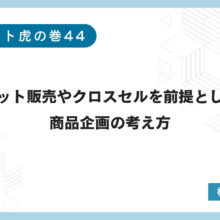
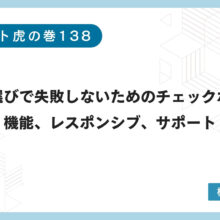
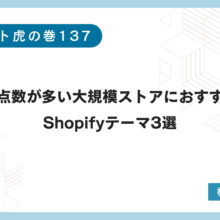
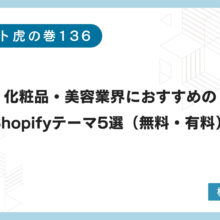
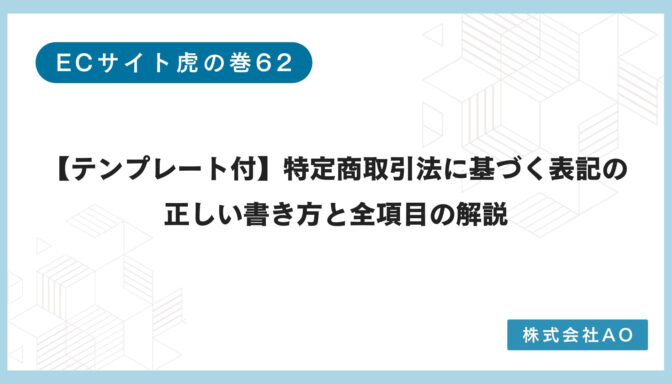
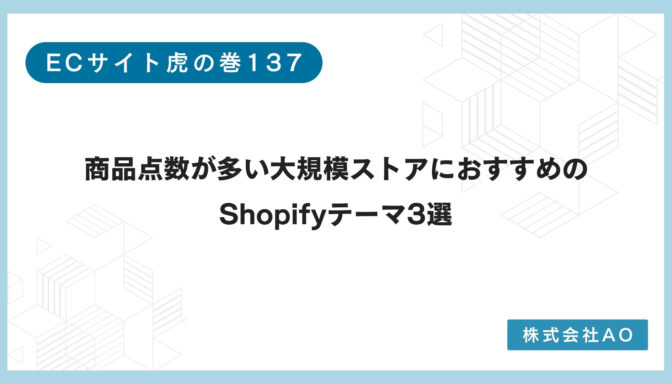

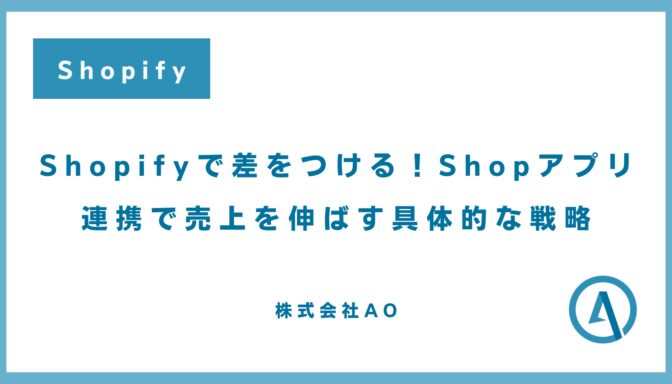








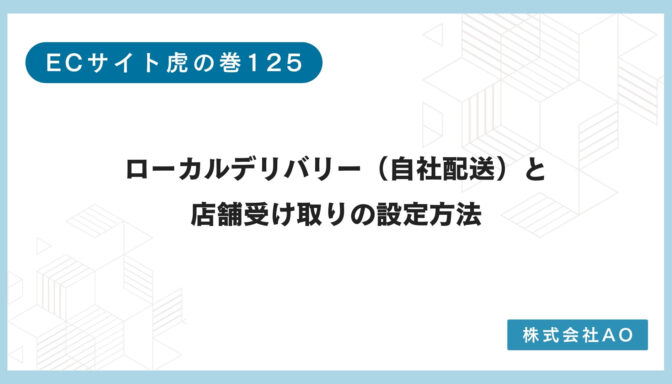
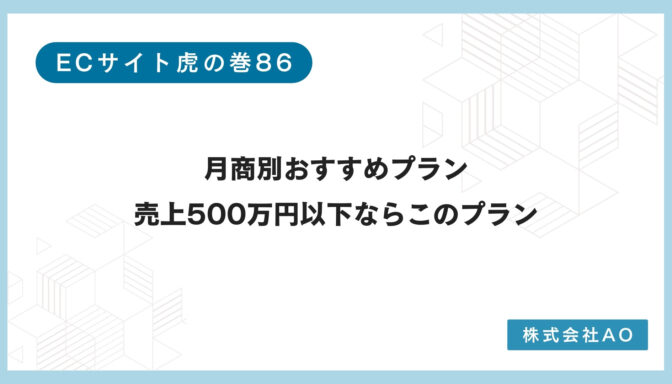

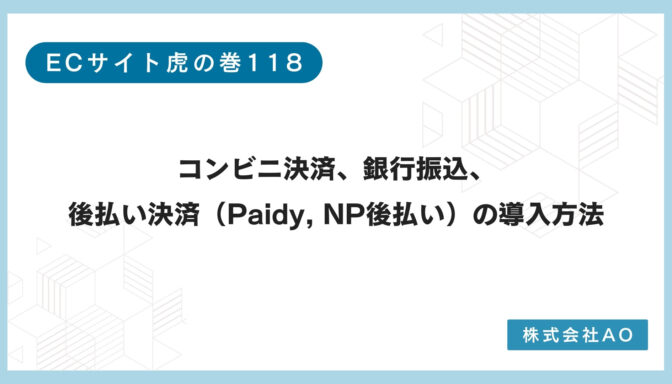



コメント