競合分析で勝ち筋を見つける!価格・品揃え・プロモーションを徹底解剖する「3P分析フレームワーク」
「競合の動きが速くて、どう対応すればいいかわからない…」
「なんとなく競合調査はしているけど、次の具体的なアクションに繋がらない…」
「データに基づいた説得力のある戦略を立てたい…」
企業のマーケティング担当者様であれば、このような悩みを一度は抱えたことがあるのではないでしょうか。市場が成熟し、顧客の購買行動が多様化する現代において、感覚だけに頼った戦略立案は非常に危険です。成功の鍵を握るのは、データに基づいた正確な競合分析です。
本記事では、数ある分析手法の中でも特に実用的で、明日からのアクションに繋がりやすい「価格(Price)」「品揃え(Products)」「プロモーション(Promotion)」の3つのPに着目した、独自の競合分析フレームワークを徹底解説します。このフレームワークを活用すれば、競合の戦略を丸裸にし、自社の勝ち筋を明確にすることができます。
なぜ今、競合の「3P」分析が重要なのか?
マーケティングの基本フレームワークとして3C分析や4P分析がありますが、情報が多岐にわたり、どこから手をつければいいか分からなくなりがちです。そこで、顧客の購買意思決定に直接的な影響を与える「価格」「品揃え」「プロモーション」の3つに絞って深く分析することで、より具体的で効果的な戦略を導き出すことができます。
- 市場の成熟化と競争激化:多くの市場で商品やサービスがコモディティ化し、他社との差別化が難しくなっています。競合の動向を正確に把握することが、生き残りの必須条件です。
- 顧客の購買行動の変化:インターネットの普及により、顧客は簡単に複数の商品を比較検討できるようになりました。競合の価格や品揃え、プロモーションは、自社の売上に直接影響します。
- データドリブンな意思決定の必要性:勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータに基づいて戦略を立案し、その効果を測定することが、ビジネスの成長に不可欠です。
競合分析を成功させる「3P」フレームワーク
それでは、具体的な分析フレームワークを見ていきましょう。このフレームワークは、「価格(Price)」「品揃え(Products)」「プロモーション(Promotion)」の3つの切り口で競合の戦略を分析し、自社の戦略立案に活かすことを目的としています。
1. 価格(Price)分析:適正な価格設定と収益最大化の鍵
価格は、顧客の購買決定に最も直接的な影響を与える要素の一つです。競合の価格戦略を分析することで、自社の価格設定の妥当性を検証し、収益最大化のヒントを得ることができます。
何を分析するか?
- 価格帯:主力商品、高価格帯商品、低価格帯商品の価格はいくらか。
- 価格設定のロジック:コストベースか、価値ベースか、競争ベースか。
- 割引・セール:どのくらいの頻度で、どの程度の割引率のセールを行っているか。
- 価格改定の動向:値上げ・値下げの頻度やタイミング、その背景は何か。
- オプション・追加料金:付帯サービスやオプションの価格設定はどうなっているか。
具体的な分析手法・ツール
- 定点観測:競合のECサイトや店舗を定期的にチェックし、価格の変動を記録します。スプレッドシートにまとめるだけでも有効です。
- Webスクレイピングツール:ツールを使って競合サイトの価格情報を自動で収集・蓄積し、効率的に分析します。
- 価格調査ツール:専門の価格調査サービスを利用し、市場全体の価格動向を把握します。
(分析例)
競合A社は、主力商品の価格を据え置きつつ、週末限定で10%OFFのクーポンを配布している。これは、平日の売上を維持しながら、週末の新規顧客獲得を狙った戦略だと推測できる。対して自社は定価販売のみ。週末の売上機会を逃している可能性がある。
2. 品揃え(Products)分析:市場のニーズと自社のポジショニングを明確に
競合がどのような商品を、どのようなラインナップで提供しているかを分析することで、市場で求められているニーズや、自社が狙うべきポジションが見えてきます。
何を分析するか?
- 商品ラインナップ:商品のカテゴリ、SKU(在庫最小管理単位)数はどのくらいか。
- 主力商品・死筋商品:どの商品が売れ筋で、どの商品が動きが鈍いか。
- 機能・特徴:各商品のスペック、デザイン、品質、独自性は何か。
- 新商品の投入サイクル:どのくらいの頻度で新商品を発売しているか。
- ターゲット顧客層:どのような顧客層をターゲットにした商品構成になっているか。
具体的な分析手法・ツール
- 機能比較表の作成:自社と競合の商品を並べ、機能やスペックを一覧表にして比較します。これにより、自社の強み・弱みが一目瞭然になります。
(機能比較表のサンプル)機能 自社製品A 競合製品B 競合製品C 機能X ● ● – 機能Y ● – ● 機能Z – ● ● - ポジショニングマップの作成:「価格」と「品質」など、2つの軸で自社と競合の商品をマッピングし、市場における自社の立ち位置を視覚的に把握します。
- 情報収集:競合の公式サイト、カタログ、プレスリリース、顧客レビューサイトなどから網羅的に情報を収集します。
(分析例)
ポジショニングマップを作成した結果、競合B社は「高価格・高機能」領域を独占していることが判明。一方、「低価格・高機能」の領域は空白地帯となっている。自社の技術力と生産体制を活かせば、このポジションを狙える可能性がある。
3. プロモーション(Promotion)分析:効果的な顧客アプローチのヒント
競合が「誰に」「何を」「どのように」伝えているのかを分析することで、効果的なマーケティングコミュニケーションのヒントを得ることができます。
何を分析するか?
- 広告チャネル:Web広告(リスティング、ディスプレイ)、SNS広告、雑誌広告、テレビCMなど、どの媒体に注力しているか。
- キャンペーン内容:どのような割引、プレゼント、イベントを実施しているか。
- メッセージング:広告やWebサイトでどのようなキャッチコピーや訴求軸を打ち出しているか。(例:価格の安さ、品質の高さ、手軽さなど)
- SNS活用:どのSNSプラットフォームで、どのようなコンテンツ(投稿、動画、ライブ配信)を発信しているか。フォロワー数やエンゲージメント率はどうか。
- インフルエンサー/広報活動:インフルエンサーの起用や、プレスリリースの配信などのPR活動は行っているか。
具体的な分析手法・ツール
- 広告ライブラリの活用:Facebook広告ライブラリなどを活用し、競合が出稿している広告クリエイティブを確認します。
- SNS分析ツール:競合アカウントのフォロワー数の推移やエンゲージメントの高い投稿を分析します。
- Webサイトの定期巡回:競合サイトのトップページやキャンペーンページを定期的にチェックし、情報の更新を追跡します。
(分析例)
競合C社は、Instagramで20代女性に人気のインフルエンサーを起用し、商品の利用シーンを投稿してもらうことで共感を呼んでいる。自社はスペック訴求の広告が中心だったが、ターゲット層によっては、より共感を重視したプロモーションが有効かもしれない。
分析結果を「勝つための戦略」に繋げる4ステップ
3P分析で得た情報は、あくまで戦略を立てるための材料です。重要なのは、その分析結果から自社が取るべき具体的なアクションを導き出すことです。
ステップ1:SWOT分析で自社の強み・弱みを再確認
3P分析の結果を、「機会(Opportunities)」と「脅威(Threats)」として整理します。その上で、自社の「強み(Strengths)」と「弱み(Weaknesses)」を洗い出し、SWOT分析のフレームワークにまとめます。
ステップ2:クロスSWOT分析で具体的な戦略を立案
SWOTの4つの要素を掛け合わせる(クロスさせる)ことで、具体的な戦略の方向性を導き出します。
- 強み × 機会(積極化戦略):自社の強みを活かして、市場の機会を最大限に活用する戦略。
- 強み × 脅威(差別化戦略):自社の強みで、競合の脅威を切り抜ける戦略。
- 弱み × 機会(改善・強化戦略):市場の機会を逃さないために、自社の弱みを克服する戦略。
- 弱み × 脅威(防衛・撤退戦略):最悪の事態を避けるための防衛的な戦略。
ステップ3:KPIを設定し、実行計画に落とし込む
立案した戦略を実行可能なレベルまで具体化します。「何を」「いつまでに」「誰が」「どのように」行うのかを明確にし、測定可能なKPI(重要業績評価指標)を設定します。(例:「新商品の売上を3ヶ月で120%にする」)
ステップ4:PDCAサイクルを回し、継続的に改善
市場や競合の状況は常に変化します。一度立てた計画を実行する(Do)だけでなく、定期的に結果を評価し(Check)、改善策を講じる(Action)というPDCAサイクルを回し続けることが重要です。競合分析も一度きりで終わらせず、継続的に行いましょう。
競合分析でよくある失敗と対策
最後に、競合分析を行う上で陥りがちな失敗とその対策をご紹介します。
- 失敗1:目的が曖昧なまま分析を始めてしまう
対策:「価格戦略を見直したい」「新商品のコンセプトを固めたい」など、分析を始める前に「何のために分析するのか」という目的を明確にしましょう。 - 失敗2:情報の収集だけで満足してしまう
対策:本記事で紹介したように、「分析から戦略立案へ」というプロセスを意識し、必ず具体的なアクションプランにまで落とし込むことをルールにしましょう。 - 失敗3:自社の視点だけで判断してしまう
対策:分析結果を評価する際は、「顧客の視点」を忘れないようにしましょう。顧客アンケートやレビューサイトの情報も参考に、客観的な判断を心がけることが大切です。
まとめ
本記事では、競合の「価格」「品揃え」「プロモーション」を分析するための実践的なフレームワークと、その結果を具体的な戦略に繋げるためのステップを解説しました。
競合は、自社の戦略を映し出す「鏡」です。継続的な競合分析を通じて自社と市場を客観的に見つめ直すことが、厳しい競争を勝ち抜くための第一歩となります。
まずは、あなたの会社の最大の競合を1社選び、今回ご紹介した「3P」の観点から分析を始めてみてはいかがでしょうか。そこからきっと、次の一手が見えてくるはずです。
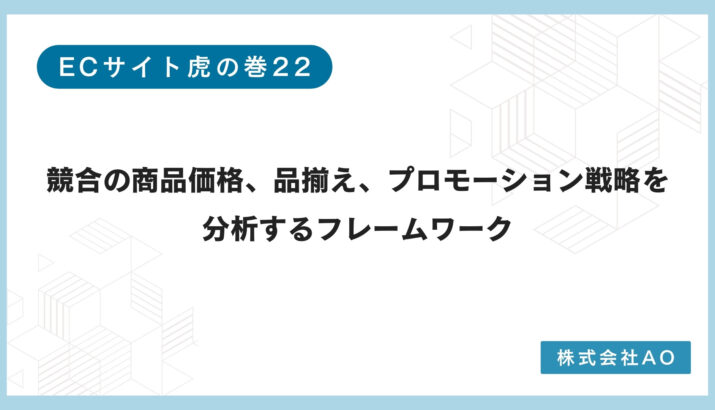
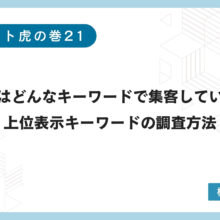
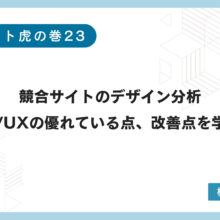
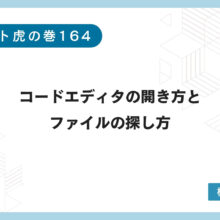
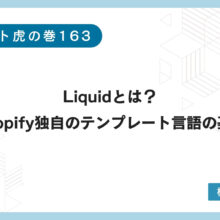
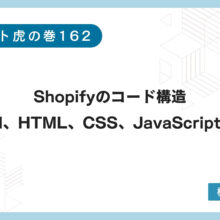



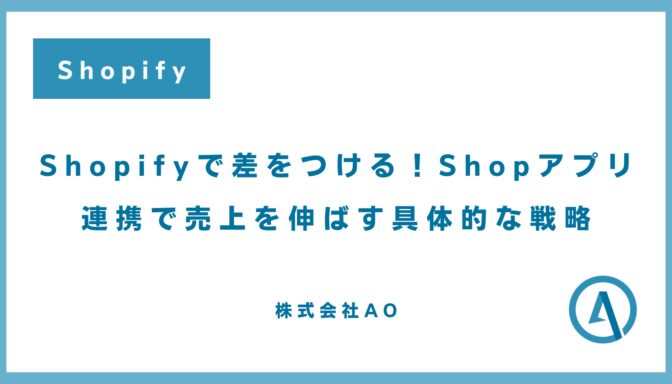








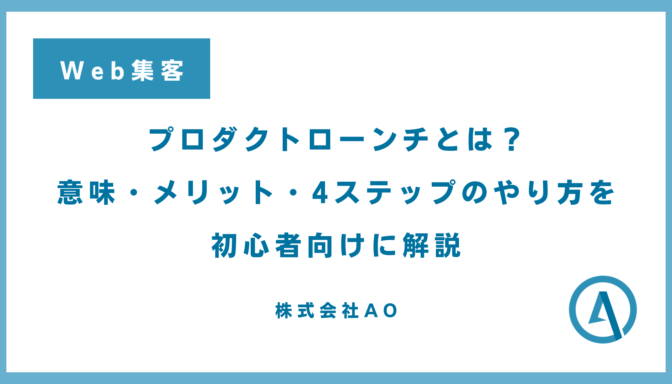


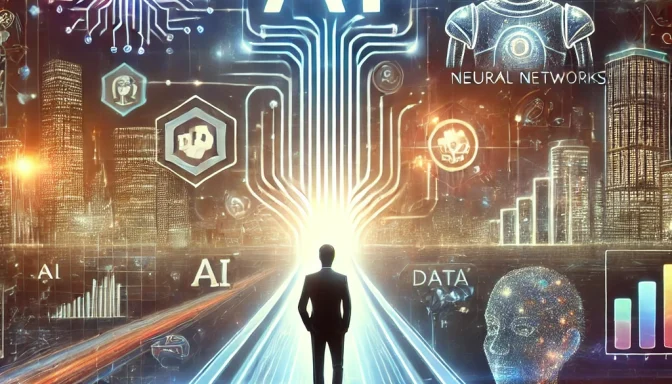



コメント