なぜアイデアは「発散」と「収束」のセットで考えるべきなのか?
「斬新なコンセプトを生み出したいのに、ありきたりなアイデアしか浮かばない」「ブレストをしても、結局まとまらずに時間切れ…」。そんな経験、あなたにもありませんか?多くのチームが陥るこの問題の根本原因は、アイデアを「出す」ことと「まとめる」ことを同時にやろうとしている点にあります。
優れたコンセプト設計は、大きく2つのフェーズに分かれます。それが、思考の枠を外してアイデアを爆発的に広げる「発散」と、混沌としたアイデアの中から本質を見出し、一つの形に磨き上げる「収束」です。この2つのフェーズを意識的に切り分けることこそが、凡庸なアイデアを鋭いコンセプトへと昇華させる秘訣なのです。
「発散」フェーズ:思考の枠を外す時間
この段階の目的は、とにかくアイデアの「量」を出すことです。実現可能性やコスト、常識といった制約は一旦忘れ、質より量を追求します。批判や結論を急がず、自由な発想を歓迎することで、普段は思いつかないような斬新なアイデアの種が生まれます。このフェーズの主役が「ブレインストーミング」です。
「収束」フェーズ:混沌から構造を見出す時間
発散フェーズで生まれた大量のアイデアは、まだ原石のままです。この混沌とした情報の中から、共通項や関係性を見つけ出し、グループ化・構造化することで、顧客の隠れたニーズやコンセプトの核となるインサイトを導き出します。このフェーズで絶大な力を発揮するのが「KJ法」です。
Step 1.【発散】ブレインストーミングでアイデアを量産する
ブレインストーミング(ブレスト)は、複数人でアイデアを出し合うことで、連鎖反応や化学反応を起こし、発想を広げていく手法です。その成功は、創造性を最大限に引き出すための「場作り」にかかっています。まずは、成功を左右する「4つのルール」をチーム全員で共有しましょう。
成功を左右する「4つのルール」
- 結論・批判の禁止 (No Criticism)
どんなアイデアも、まずは受け入れましょう。「でも」「しかし」といった否定的な言葉はアイデアの芽を摘んでしまいます。「いいね!」「面白いね!」と肯定的な雰囲気を作ることが重要です。 - 自由奔放な発想 (Freewheeling)
「こんなことを言ったら笑われるかも」という恐れは不要です。常識を疑い、突拍子もないアイデアや非現実的なアイデアこそ歓迎しましょう。そこから新しい発想が生まれます。 - 質より量 (Quantity over Quality)
この段階では、一つひとつのアイデアの質は問いません。目標は、とにかくたくさんのアイデアを出すことです。100の平凡なアイデアの中に、1つの非凡なアイデアが隠れています。 - 便乗・結合・改善 (Combination and Improvement)
他人のアイデアに便乗し、発展させることを積極的に行いましょう。「〇〇さんのアイデアに、△△を組み合わせたらどうだろう?」といった形で、アイデアを結合・改善していくことで、一人では思いつかなかったようなアイデアが生まれます。
ブレインストーミングの実践的な進め方(5ステップ)
- テーマ(問い)を明確にする:具体的で、ポジティブな問いを設定します。(例:「若者が毎日飲みたくなるプロテインとは?」)
- 準備物を用意する:付箋(ポストイット®)、一人一本のペン、ホワイトボードや模造紙を用意します。
- 個人ワーク:まずは5〜10分、一人で黙々とアイデアを考え、1枚の付箋に1つのアイデアを書き出します。
- 全員で共有:一人ずつ順番に、書き出した付箋を読み上げながらホワイトボードに貼っていきます。この時、他の人はアイデアの補足説明を求めたり、批判したりしないようにします。
- アイデアの結合・発展:ホワイトボードに貼られたアイデアを全員で眺め、新たなアイデアが浮かんだら、どんどん付箋に書いて追加していきます。ルール4の「便乗・結合」を意識しましょう。
【コツ】本題に入る前に、「理想の休日の過ごし方」のような簡単なテーマで練習をすると、場の空気が和らぎ、発言しやすくなります。
Step 2.【収束】KJ法でアイデアを構造化し、本質を見抜く
大量のアイデアが出揃ったら、次は収束のフェーズです。ここで役立つのが、文化人類学者の川喜田二郎氏が考案した「KJ法」です。KJ法は、一見バラバラに見える情報(付箋)を、その内容の親和性(似ている、関係性が近い)によってグループ化し、図解することで、情報の背後にある構造や本質的な意味を明らかにする手法です。
KJ法の具体的なやり方(5ステップ)
- カード化:ブレストで使った付箋がそのまま「カード」になります。1枚のカードに1つの情報が書かれている状態が理想です。
- グループ編成:ホワイトボードに貼られた全てのカードを一度剥がし、机の上に広げます。そして、「なぜか気になる」「これとこれは仲間な気がする」という直感を頼りに、内容が似ているカードを集めて小さなグループを作っていきます。無理に分類しようとせず、しっくりこないカードは一枚のままで構いません。
- グループ名の作成:各グループのカードが言わんとしていることを最も的確に表すタイトルをつけ、新しい付箋に書いてグループのそばに置きます。元のカードの言葉を要約するだけでなく、そのグループが持つ「意味」や「価値」を表現する新しい言葉を生み出すのがコツです。
- 図解化(親和図):グループ名を書いた付箋をホワイトボードに貼り直し、グループ同士の関係性を考えながら線で結んでいきます。グループの位置関係を動かしながら、「これが原因で、これが起きる(矢印)」「これとこれは対立している(⇔)」といったストーリーを声に出しながら整理すると、思考がクリアになります。
- 文章化:完成した図解(親和図)を眺めながら、そこから読み取れるストーリーを文章にまとめます。「〇〇という背景・課題があり(原因)、顧客は△△という価値を求めている(本質)。したがって、我々は□□という解決策を提供すべきだ(コンセプト)」といった形で記述します。これが、コンセプトの骨子となります。
【実践例】「新しいプロテイン」のコンセプトを考えてみよう
では、先ほどのテーマでブレストとKJ法を行った場合、どのようにコンセプトが生まれるか見てみましょう。
ブレストで出たアイデアの断片(付箋のイメージ)
「SNS映えするパッケージ」「筋トレ感をなくしたい」「朝食の代わりになる」「毎日飲んでも罪悪感がない」「まるでデザート」「コンビニで手軽に買いたい」「美容成分も欲しい」「自分へのご褒美感が大事」「腹持ちが良い」「シェイカーが不要」……など多数。
KJ法でグループ化・図解化
これらの付箋をKJ法で整理すると、以下のようなグループと関係性が見えてきました。
- Aグループ「ご褒美スイーツ感覚」
(まるでデザート、ご褒美感が大事、罪悪感がない) - Bグループ「多忙な日々の時短ツール」
(朝食の代わり、コンビニで手軽に、シェイカー不要) - Cグループ「カラダの内側から美しく」
(美容成分も欲しい、SNS映え、筋トレ感をなくしたい)
【関係性の発見】
図解化していく中で、「多忙なライフスタイル(B)の中で、手軽に美容(C)もケアしたいという強いニーズがある。その解決策は、義務感で飲むものではなく、楽しみながら続けられるスイーツ(A)のような存在ではないか?」という構造が浮かび上がってきました。
導き出されたコンセプトの骨子
「忙しい毎日を送る若者が、罪悪感なく楽しめる『ご褒美スイーツ』のような感覚で、手軽に美容と健康をチャージできるプロテインドリンク」
よくある失敗と成功のコツ
- ブレストの失敗:司会者(ファシリテーター)が仕切りすぎてしまったり、沈黙を恐れて結論を急いだりすると、自由な発想が生まれにくくなります。ファシリテーターは交通整理役に徹し、沈黙も「アイデアを熟成させている時間」と捉えましょう。
- KJ法の失敗:最初から大きなカテゴリーで無理やり分類しようとしたり、グループ名が元のカードの言葉の単なる要約で終わってしまったりすると、本質が見えてきません。直感を信じて小さなグループから作ること、グループの本質を捉えた新しい言葉を生み出すことを意識しましょう。
- 成功のコツ:近年では、MiroやMuralといったオンラインのホワイトボードツールも充実しています。リモートチームでも、これらのツールを使えば付箋を使ったワークショップが可能です。
まとめ
優れたコンセプトは、ただ一人の天才がひらめくのを待つだけでは生まれません。チームの多様な視点を掛け合わせ、創造性を引き出す「仕組み」が不可欠です。
ブレインストーミングで思考のタガを外し、アイデアの量を最大化する。そして、KJ法で混沌の中から意味のある構造を見出し、質を高めていく。この「発散」から「収束」へのプロセスが、ありきたりなアイデアを、人の心を動かす鋭いコンセプトへと昇華させます。
完璧にやろうと気負う必要はありません。まずはあなたのチームで楽しみながら、付箋とペンを手に取ってみてください。対話と試行錯誤の中から、きっと未来を切り拓くコンセプトの種が見つかるはずです。
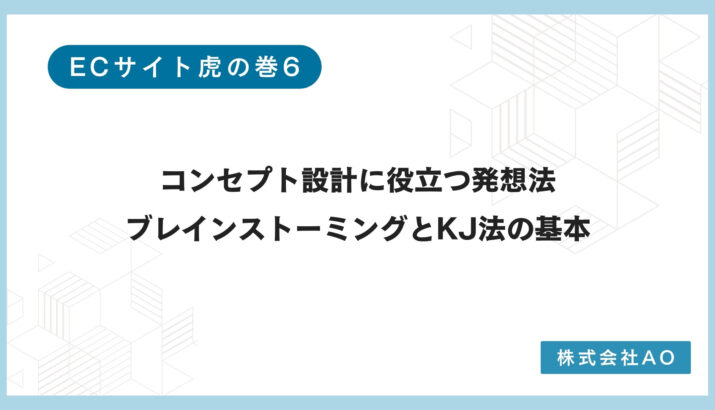
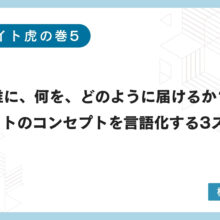

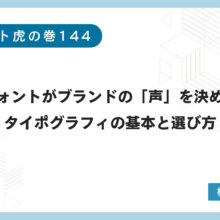
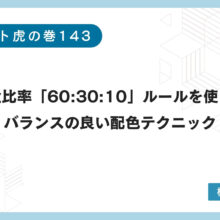
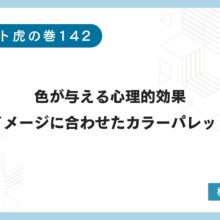



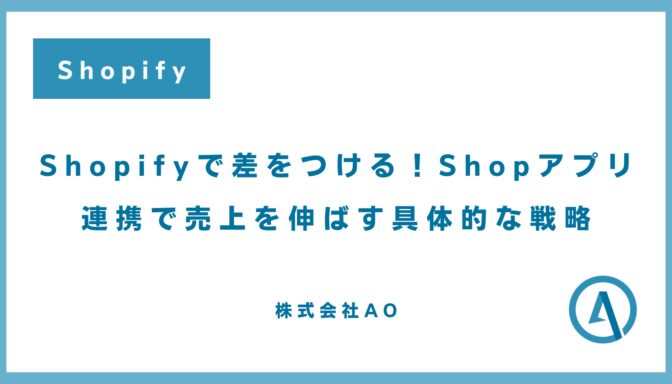








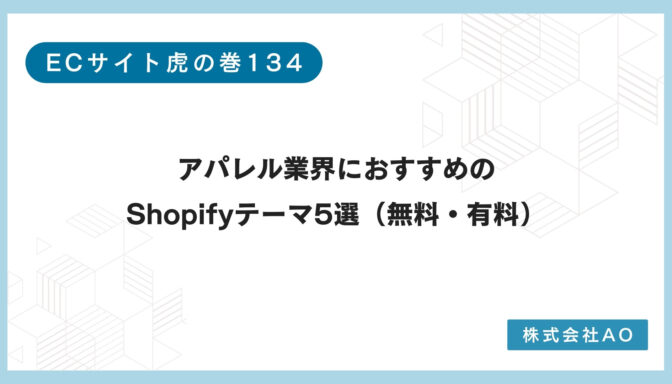

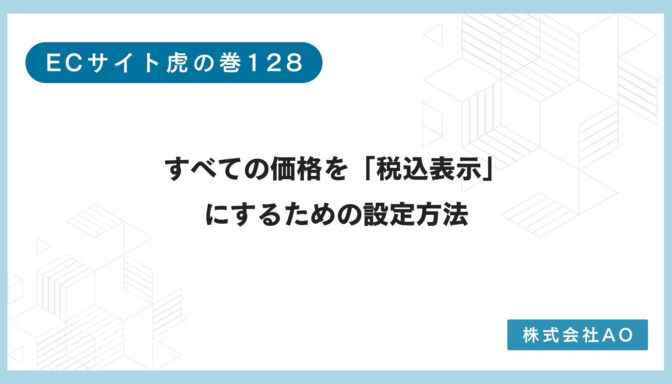
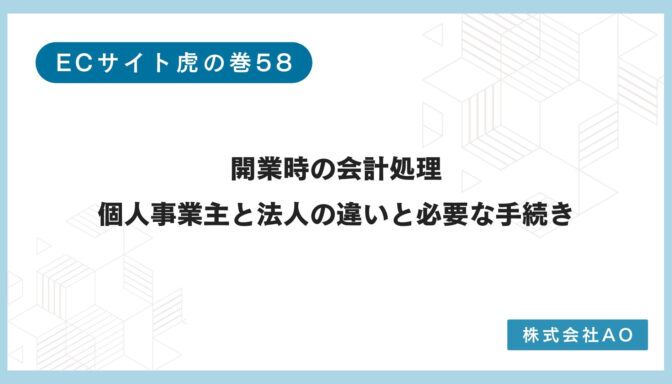



コメント